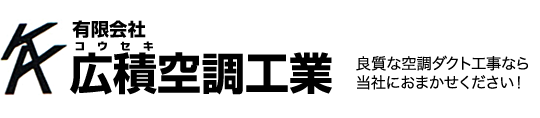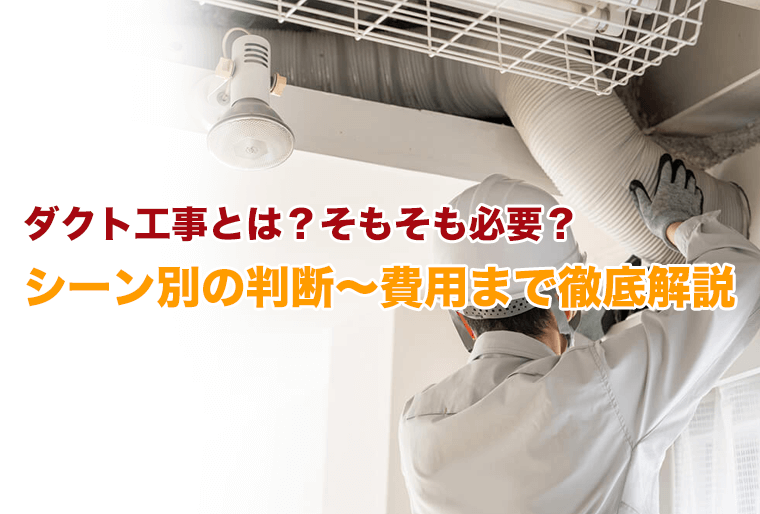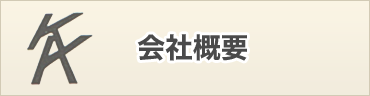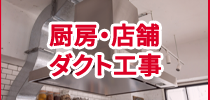ダクト工事の工法「はぜ」とは?知るとおもしろい歴史・豆知識

ダクトをはじめ板金をつなぎ合わせる際には「はぜ」という工法を使うことがあります。よく使われている工法ですが、実は非常に歴史が深く、手作業で行う場合は熟練した技術が必要となります。私たちもダクトの配管をつなぎ合わせる際に、この工法を使うことがあります。
今回はダクトに関連した読み物としてはぜとはどんな工法なのか?どんな歴史があるのか?についてご紹介します。
目次
ダクト工事の工法「はぜ」とは?
冒頭のとおりはぜとは板金同士をつなぎ合わせる工法のことを指します。2枚の板金の接合部をそれぞれ折り曲げ、お互いの折り目に引っ掛け合わせてつなぎ合わせます。
板金の接合したい部分を重ねて直角に折り曲げ、さらに曲げます。その後、上から叩いて平らにし、さらに「たがね」と呼ばれる工具を使ってしっかりと固定します。
はぜには、外側から内側に向かってUの字型に折り込む「ダクトはぜ」、板金をヘアピンのように折り曲げる「ピッツバーグはぜ(三井はぜ)」、外側と内側の板金をUの字状に折り曲げてつなぎ合わせる「側面はぜ」など、さまざまな種類があります。
なぜ「はぜ」を用いるのか?
はぜはダクトの配管をつなぎ合わせる際によく用いられる工法です。他にも溶接やカシメなど、板金同士を接合する工法はさまざまあるのですが、はぜを活用するのには理由があります。
まず挙げられるのは気密性が高いということです。はぜは2枚の板金を折り重ねるため、気体や液体が漏れにくいという利点があります。缶にもはぜの技術が応用されているほどです。
耐久性が非常に高いのもはぜを採用する利点です。板金の接合部はどうしても強度が低くなりがちですが、はぜの場合は2枚の板金が折り重なっているゆえ、強度が他の工法よりも高くなります。
ダクトの配管は空気や水蒸気、油などが絶えず通る過酷な環境に置かれます。仮に気体や液体が漏れたら重大なトラブルにもつながりかねません。気密性と耐久性が高いはぜは、ダクトにはうってつけの工法なのです。
現代日本のダクト工事と「はぜ」の歴史
 ダクトの配管をつなぎ合わせる際によく使われるはぜですが、その歴史は非常に長く、明治時代にまで遡ります。ここからははぜの歴史について紐解いていきましょう。
ダクトの配管をつなぎ合わせる際によく使われるはぜですが、その歴史は非常に長く、明治時代にまで遡ります。ここからははぜの歴史について紐解いていきましょう。
【明治時代】ダクト工事と「はぜ」の普及
日本にはぜの技術が伝わってきたのは明治の初期、洋風建築の技術が入ってきた頃といわれています。屋根は野路板の上に防水材を施工し、その上に屋根材を被せるという構造になっており、屋根材と屋根材を接合する際にはぜという工法が使われるようになりました。なお、それまででも鉄板や銅板を屋根に用いることはありましたが、はぜが使われだしたのは明治初期からといわれています。
その頃から建物にアメリカのダクト製造技術が使われるようになり、赤坂離宮(現在の迎賓館)にもその技術が活用されました。江戸時代の屋根職人がはぜの技術が伝わってから鐵板屋根の職人に転業し、ダクトも施工するようになったそうです。
【昭和初期①】手作業で組み立てる「本はぜ」
赤坂離宮でアメリカのダクト技術が採用されたのは前述のとおりです。当時の造営局の職人がダクト職人の親方に指導を行い、大正から昭和初期にかけて国内においてもアメリカのダクト技術、そしてはぜという工法が普及してきたとされています。
当時は本はぜという工法が主流で、これははぜの中でももっとも歴史が古い工法といえます。接合部をUの字状に折り曲げてつなぎ合わせる「甲はぜ」と、接合した後に一方の板金を直角に折り曲げる「角甲はぜ」の2種類があり、これらの工法が昭和初期に確立され、当時の建築に使われていたのです。当時はもちろん手作業ではぜ加工を行っていました。
【昭和初期②】長いダクトも作成可能に「ピッツバーグはぜ」
ピッツバーグはぜは一方の板金を叩き込んで、さらに2回ヘアピン状に折り曲げます。2回目に折り曲げたときにできた溝に、もう一方の板金を入れた後にさらに折り叩き込むことで、2枚の板金を接合することができます。本はぜと比較して複雑な加工が必要になりますが、その分強度が高いという利点があります。
1930年ころにアメリカ人の技術者によって伝えられ、国内では三井銀行本店の工事ではじめて採用されたということから、「三井はぜ」とも呼ばれています。
それ以降、本はぜに加えてピッツバーグはぜ(三井はぜ)も盛んに使われるようになりました。高い強度と気密性が実現できるこの工法が確立されたことで、従来よりも長いダクトが製造できるようになりました。
【昭和中期】機械織りで効率化「ボタンパンチスナップはぜ」
1930年代にはアメリカではぜ折り機が開発され、機械化が進んできました。しかし、当時は第二次世界大戦の頃で日本とアメリカは断交状態。日本におけるはぜの機械化は大幅に遅れることとなりました。
戦争が終わって1957年、日本においてもようやくはぜ折り機が市販され、はぜの加工やダクト製造の機械化が進んだのです。
また、昭和中期にはボタンパンチスナップはぜという新しい工法も使われるようになりました。二重に折り返した板金のスキマに、スナップ加工された板金を引っ掛けて叩き込み接合する工法です。
高度経済成長期には機械化と工法の多様化が進み、日本においても独自のダクト技術や加工法が確立され、それが今日のダクト製造にも息づいているのです。
ダクト工事には昔からの技術が欠かせない
 今、多くの製品は機械で造られており、人間が手作業を行うことが少なくなりました。もちろん、ダクト製造の現場も例外ではありません。しかし、ダクトはお客様のニーズや建物の構造などによって配置が異なります。そのため、完全に機械化することはできません。
今、多くの製品は機械で造られており、人間が手作業を行うことが少なくなりました。もちろん、ダクト製造の現場も例外ではありません。しかし、ダクトはお客様のニーズや建物の構造などによって配置が異なります。そのため、完全に機械化することはできません。
ダクトを製造する際、あるいは配管をつなぎ合わせる際には、今でも昔ながらのはぜ工法を使い、手作業をすることも多いです。
まとめ
はぜという工法は明治時代に日本に伝わった非常に歴史が長い工法ですが、今でもそれが現場で使われているのです。もしも、はぜの技術が日本に伝わっていなかったら、高品質なダクトを製造・施工することはできないでしょう。職人の間で脈々と受け継がれてきたはぜの技術を使って世の中のお役に立てることに誇りを感じています。また、この技術を後世に伝えていくのも私たちの役目だと考えております。
広積空調工業では職人がさまざまな技術を用いてお客様のご要望や建物に合わせたダクトを設計・製造・施工しています。完全自社施工なので、高品質なダクトを適正価格でご提供可能です。東京、千葉、埼玉、茨城のダクト工事なら、ぜひ私たちにお任せください。
≪前へ「ダクトとはどんなもの?プロがわかりやすく徹底解説します!」 | 「排煙ダクトは必要?役割と重要性をわかりやすく解説」次へ≫